車、工場、モノ、人、社会のさまざまな課題を解決

高速道路の交通渋滞は連休のたびに映し出される恒例の光景です。この現象を解決できるのは「ゆとり」であると渋滞学を提唱した東京大学教授の西成活裕様は考えています。さらに、その考え方を応用することで、車や人以外にもさまざまな分野の渋滞を解消してきました。製造業においてもDX推進による業務改善を行う場合、業務フローに無駄があるか、効率的に流れているかを可視化し、問題点を明らかにすることが重要です。渋滞学の観点から改善策を講じる上での考え方について西成先生にお話を伺いました。
宇宙戦艦ヤマトから
渋滞を解消する研究へ
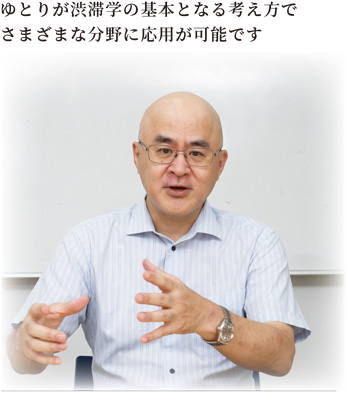
工学系研究科航空宇宙工学専攻
先端科学技術研究センター(兼任)
教授
西成 活裕 様
- ・1967年東京都生まれ。
- ・東京大学大学院工学系研究科博士課程修了、工学博士。専門は数理物理学、渋滞学。
- ・山形大助教授、龍谷大助教授、ドイツのケルン大学理論物理学研究所客員教授などを経て、現在は東京大学工学系研究科航空宇宙工学専攻教授。
- ・日本国際ムダどり学会会長、MUJICOLOGY!(ムジコロジー)研究所所長などを歴任。
- ・さまざまな渋滞を分野横断的に研究する「渋滞学」を提唱し、著書「渋滞学」(新潮選書)は講談社科学出版賞などを受賞。
- ・文部科学省「科学技術への顕著な貢献 2013」に選出。
- ・2021年イグ・ノーベル賞を受賞。
- ・東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会アドバイザーに就任、国交省、経産省、文科省などの有識者委員も多数務めている。
- ・日経新聞「明日への話題」連載、日本テレビ「世界一受けたい授業」に多数回出演するなど、多くのテレビ、ラジオ、新聞などのメディアでも活躍している。
- ・趣味はオペラを歌う事、そして合氣道の稽古。
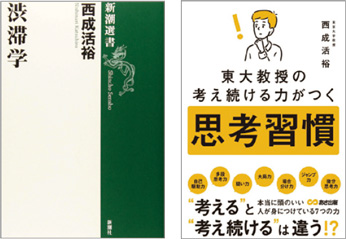
東 この度は、対談をご快諾いただきありがとうございます。西成先生が研究されている渋滞学から、製造業を中心とした私たちのお客さまへご助言いただければ幸いです。それでは、西成先生が確立された渋滞学について改めてお伺いしたいのですが、まずは、渋滞学を研究されるまでの経緯をお聞かせいただければと思います。
西成 こちらこそ、本日はどうぞよろしくお願いいたします。今は渋滞学を研究していますが、大学では航空宇宙工学を専攻していました。子どもの頃から宇宙に憧れていて、宇宙戦艦ヤマトが大好きでした。宇宙に行ってみたいという夢があり航空宇宙に憧れて、その基礎となる数学や物理学の勉強を続けているうちにそちらが楽しくなってきました。やはり学んだことで社会の役に立ちたいとは考えていましたが、数学や物理だけでは難しいと悩んでいたところ、ぱっと渋滞の研究がひらめきました。それが35年前です。最初の10年ぐらいは学会で相手にされない時期を過ごしましたが、実際のところ皆さん渋滞を解消したいと思っていて、私のアイデアを投入するとうまくいくことが増え始め、さまざまな分野から相談されることが多くなりました。2006年に渋滞学の本を執筆した頃から、数学や物理、シミュレーションなどを使って解決するスタイルが確立しています。渋滞学で大事なことを一言で言えば、ゆとりです。それが私のオリジナルの考え方です。
東 車の渋滞は避けたいですね。今後、自動運転技術が進化、普及すると渋滞は解消されるのでしょうか。
西成 車間距離の詰めすぎが渋滞の最大の原因だということが、いろいろなデータと実験から分かっています。高速道路では車間距離40メートルというのが渋滞解消のポイントになります。40メートル以下だと前の車がブレーキを踏むと、自分の車も危ないからブレーキを踏みます。さらに後ろの車はより強くブレーキを踏んでしまいます。40メートル以上離れていれば、ブレーキを踏むかもしれないけれど、弱く踏むので渋滞にならないのです。その臨界があるというところがミソで、すべての車両が混んできても車間距離40メートルというゆとりを保てば、渋滞は起きません。
また、自動運転の車で実験を行ったことがあります。車両同士が通信で情報を共有していると、先頭の車がブレーキを踏んだ際に、その情報が最後に並んだ車まで伝わり、事前にブレーキを踏む準備ができるため、反応が早くなり、渋滞が減ります。そうした時代はまだ少し先ですが、一般の車がすべてつながれば、渋滞は減少するでしょう。
東 西成先生の「渋滞学」の本で、車、人以外にも渋滞になる原因、解決策について拝読しました。さまざま分野で渋滞があり、その解決の糸口がありますね。
西成 その本では、車や人だけでなく、生物でいうとアリの渋滞について書いています。私がアリの研究を行って、世界で初めてアリは渋滞しないことを見つけました。アリの群れを調べてみたのですが、アリは車間距離ならぬアリ間距離を空けておくんですね。自分の体長分ぐらいの間があって、混んできても詰めないという戦略で、渋滞を回避していました。それと比べると人間は、早く行こうとして、皆が詰めて動けなくなります。私たち人間はアリ以下だという論文を書いたことがあります。だから、アリを見習っていかに余裕を持たせるかがポイントです。例えば、個人のスケジュールにも当てはまります。東社長もお忙しいので、やっぱりパンパンなスケジュールなのでしょう。そうすると、何かがズレると玉突き事故を起こしてしまいます。
東 おっしゃる通り、よくズレが起こっています。
西成 そうなると、その後の対応が大変になることが多いと思います。そういう方には、1日のスケジュールが最大で8件だとしたら、7件に減らしませんかとアドバイスします。実際に試してもらった銀行の頭取の場合、メールチェックが自分でできるようになり、頭を整理する時間も取ることができミスも減りました。このゆとりが一番のキーだったようで顔つきまで変わったということです。
これが車間距離でいうちょうどいい40メートルです。60メートルだと空けすぎで20メートルだと詰めすぎになり、ここを見つけるというのが肝なのです。
渋滞を絆に他の分野と
共同研究を実施

代表取締役社長
東 和久
Kazuhisa Higashi
東 今伺ったスケジュールのことなど、さまざまな分野で西成先生の渋滞学が生かされていますが、どういうきっかけで広がりを見せたのですか。
西成 一般向けに本を書くなど情報発信が増えたことで、渋滞と聞いて興味を持った人たちからの問い合わせが増えました。ある日、医学部の先生から話を聞かせてほしいという連絡がありました。その先生は、認知症の研究をしているのですが、アルツハイマー病は神経細胞の中でタンパク質がうまく動いていないことで発症するそうで、渋滞学が活用できないかという相談でした。たまにしか動かないタンパク質をサンデードライバータンパク質という、日曜日にしか運転しない運転が苦手な人に例えるそうです。つまり体の中の渋滞の研究です。バイパス手術もバイパス道路みたいな話ですよね。そういうアナロジーがたくさんあるのですが、誰も本気で車の渋滞解消を治療に結びつけようとは思わなかったということで、共同研究が始まりました。
東 アルツハイマー病と渋滞とは、よほどでないと思いつかない組み合わせですね。
西成 感度が高い人が周りにたくさんいて、渋滞と聞いてちょっとピンときたということが多いのです。
東 それぞれ違う視点で渋滞を捉えていくということは、難しいことも多いのではないですか。
西成 これまで数多くの共同研究がありましたが、これだけ医学、農学、経済学などさまざまな分野の専門家の方と論文を書いた人というのは、ほぼいないと思います。
私からすると、全部同じなんですね。渋滞が専門なので、他の分野について自分がそんなに知識があるわけではないのですが、専門家やプロの方から2年ぐらい教わると理解が進んで、その学会でも発表できるようになります。いろいろな分野とつながることができて面白いです。
企業の業務にも
生かせる渋滞学
東 企業とも連携して、いろいろなアドバイスをされていると伺っています。どのような内容になりますか。
西成 渋滞学という本の中で、物流も含めたものづくりのいろいろな現場で渋滞学が活用できるはずという記述を入れたのですが、それがきっかけで100社以上の企業の改善に協力させていただきました。
東 ものづくりの現場にもゆとりが必要で、安全や安心に生かされるということですね。生産性の向上にもつながるのではないですか。
西成 そうなんです。生産現場などで、稼働率100%ということは、渋滞学では車間距離がほぼゼロで走っている状態と同じです。社員のけがや病気、機械の不調などが出ると、すべてに影響してしまいます。そこで、機械の稼働率を例えば90%に抑えることをアドバイスします。まずは渋滞が起きないためですが、それがプラスになることも多いのです。稼働率を90%にすることで10%の空きができれば、試作品や急ぎの依頼にも対応できるようになります。急ぎの仕事で値段が上がれば、利益も増えることになります。
つまり、余裕のなさが問題であって、ゆとりを入れることで逆に生産性を上げようという逆転の発想が根本にあります。これが渋滞から学んだことで、すべてがそこに通じています。東 ゆとりは大切ですね。私たちの会社ではワークインライフを提唱しています。仕事は人生の一部であって、仕事もプライベートも大切にしながら人生の充実を考えようということで、働き過ぎを止めてゆとりを持つように進めています。また打ち合わせのあり方も考える必要があります。打ち合わせばかりが多くて、作業は18時からでなければ行えないとなると生産性が上がりません。これからは18時以降のタイムマネジメントは個人で決めるように言っています。でも皆仕事が好きなようで、実現は難しいですね。やはり、意識改革が重要だと思いますが、成功事例がありましたらお伺いできませんか。
西成 一番難しいところだと思います。東社長もおっしゃっているとおり意識は容易に変わらないのです。実は私も、働き方改革が進められた時にアイデアを求められて、渋滞学のゆとりで改善しようとして、うまく進まなかったことがありました。その中でも成功した事例では、まずモチベーションの高い3~4人の社員を集めて、社長直属のパイロットチームを作りました。そこでマニュアルなどを作って、専門性の高くない業務は誰でも手伝えるように分散することで、全員の負荷を減らしてもらいました。答えは簡単なのです。専門性が高い業務でも手伝えることがありますから、多能工化すればいいのです。パイロットチームで実践したところ、かなりの成果が出ました。それを社内に宣伝してもらうと、共感する社員が出てくるんですね。そうやって展開していきました。
渋滞学
車や人の渋滞は誰しもイライラするものです。一方で、森林火災で火の進む勢いがなくなる「火災の渋滞」や「行列のできる店」など、適度な渋滞や停滞が望ましいケースもあります。
いろいろな性質や顔を見せる渋滞に着目した西成先生は、自由な発想から新たな学問である「渋滞学」を提唱しました。
セルオートマトン法やASEP(エイセップ)などを使った数理物理学による分析、コンピューターによるシミュレーション、多くの実証実験、他分野の専門家たちとの共同研究などを行ってきました。そこから見えてきた渋滞の本質は、さまざまな分野に応用できるものでした。



大局力で見える
無駄に見えて無駄ではないもの
東 意識改革は、全体の流れや段取りを考えて取り組むことが重要ですね。
西成 そういう長い目で見る力、大局力は欠かせないと思います。
いつも学生に言っているのですが、思考体力を鍛えるのに一番大事なポイントが、自分にやる気があるのかどうかという自己駆動力、どこに向かうかを見極める大局力、思考を積み重ねていく多段思考力の3つです。
大局力は時間軸を長い目で見ることです。自動車関連のメーカーの例ですが、コストを下げるために内製から外注に変えたことで業績を向上することができましたが、気がついた時には内製で培ってきたノウハウがすべてなくなっていたそうです。失敗も含めて、思考の過程は全部外に行ってしまい、納品されるのは成果としての製品だけでした。これだと長期的に見ると大変な損失です。
それは人も組織も同じで、長期的な視野が思考体力につながります。短期で見ると無駄に見えるけど、長期的に考えると無駄ではありません。時間軸を長く捉えることで無駄ではなくなることが、人生を長く生きていると分かってきます。魅力的な上司というのは過去に失敗している人で、そこに人間の面白さが出ます。うまくいき過ぎるとかえって失われてしまうことも多いと考えていて、それを無駄学と呼んでいろいろなところで話をさせていただいています。
東 最近、5年・10年先の中期経営計画を作成しない企業が増えていると聞きます。3年ごとに経営計画を見直しているのだから、その先は意味がないということらしいのですが、実際に成長していく会社というのは10年先のことを見据えて、それをベースに中期経営計画を作っています。未来の姿を考えておくことが重要で、3年たって計画が違ってきたら変えればいいだけで、短期的には無駄に見えても長期で考えると無駄ではないという先生の無駄学につながるものだと思います。
西成 今の学生はタイムパフォーマンス、いわゆるタイパが良くないから正解だけを聞いてくる傾向が強くて、無駄を嫌がります。これでは技術力がガタ落ちです。海外の教育は、単に教えるのではなくてディスカッションをさせることが多くあります。最近、日本の高校の視察に行ったとき、先生が投げかけたテーマで、グループごとにディスカッションして発表する授業がありました。正解がないこともあるわけで、ある意味でタイパがすごく悪いのです。でも、そういう議論をさせる時間は大切で、その授業を見てちょっと救われた気がしました。
東 社会に出ると本当に正解があるかどうかも分からない答えを探すことがあります。ゴールにたどり着くまでにどの道を通るかということが重要です。短絡的に答えだけを求める最近の傾向は怖いですね。
西成 タイパ重視だとAIが出してきた答えをそのままインプットしてしまうこともあるでしょう。今まで3日かかったのが 5分で結果を得られるので、そこは労働生産性が上がります。内容を理解している人がAIを使うのは良いと思います。知識がない若者などが使うことは、長い目で見ると逆に損になると思います。長期的な視点で試行錯誤していないことになるので、これからどうなっていくのか、10年後の世の中が懸念されます。
東 実社会では、AIを使っていかないともう無理だと思います。問題は、その内容を判断できる人材育成にどう取り組んでいくかということです。私たちの世代はAIがない時代から苦労してきたので見た瞬間にこれはうそだなと分かりますが、経験がないとそれが難しいですね。判断できる人間を育成していくには、私たちだけでなく大学の責任も大きいと思います。
西成 AIをはじめとするツールをうまく使わないといけませんね。AIは知的領域に深く入り込んでいて、AIの能力が人間を超える技術的特異点が徐々に近づいているように感じています。
多段思考力をつけることで、AIに毒されないようにするためにも学生には読書を勧めていて、図書室を作って私個人の蔵書を置いています。学生にとって、読書は一番タイパが悪くキュレーションサイトで要約を見て読んだ気になっているのです。本を読むことは、自分の中の経験と照らし合わせながら、いろいろなことを再構成していく時間であり、多段思考力を養うことになります。
東 私も読書が大好きなので大賛成です。渋滞学に始まり、無駄学、大局力、多段思考力など有益なお話を伺えました。本日はありがとうございました。
