| 環境工学研究所 理事長 スパイラルシステムズ 代表 水野 紀一 様 |
略歴

スパイラルシステムズ 代表
水野 紀一 様
| 1940年生まれ |
| 慶応義塾大学・大学院工学研究所修了 |
| 品質保証を中心としたTQC/TQMの指導 |
| 三菱重工業、久保田鉄工、清水建設、関東自動車工業等デミング賞の指導 |
| 株式会社品質経営研究所 社長 |
| QC/TQM、PL、CEマーキング、新規事業開発、ISO9000、ISO14000などの研究、指導にあたる。 |
| 現在、中小企業を中心にISO9000、 ISO14000のコンサルティングを行うとともに、中小企業のインビジブルスキル(潜在的技術)の発掘と、ネットワークを活用した新規事業の立ち上げ等の支援を行っている。 また、環境を中心とした協同組合、社会教育、環境などのシンクタンク、NPOを 立ち上げている。 |
| 主な著書 「管理技術教室」日本規格協会、「品質機能展開」日科技連 「品質業務のチェックリスト」税務経理協会「絵で見るTQC」産業教育センタ)等 |
ISO9000の概要

取締役 福武 映憲
福武 ISO取得のためのコンサルティングや、環境を中心としたNPOでご活躍しておられる水野先生に、ISOの概要、企業がISOを取得する際の取り組み方などについて、お話をお伺いしたいと思っております。
水野 我々が規格をイメージするときに、たとえば製品だったら、どんな寸法でどんな材質で、どの高さから落としても大丈夫だとか、細かい仕様が決まってますよね。こういう規格を仕様規格と言います。モノの仕様が取り決められているものです。
最近のトレンドでは、性能規格があり、代表的なものは安全性です。性能規格は、例えば安全性を確保するためにここはこうしなくちゃいけないと、仕様規格のように細かいところまで決めてはいません。こういう危険がないようにしなさいというのを決めているのが性能規格です。
技術が熟成していないときは、熟成させるためにあまり細かいことまで決めない規格を作ろういう考え方があります。そういう規格を性能規格といいます。
ISO9000とかISO14000は、性能規格でもないし仕様規格でもない。マネージメントのシステムの規格ですから、いわば経営管理のあり方に対してこうあるべきだと書いてあるのです。いろいろな業種に適応するために、必要最小限のことしか書いてありません。ところが、読む人は仕様規格のような読み方、事細かに書いてあるようなイメージで読んでしまいます。日本の人は、みんな受験生になって細かいところまで見る。そうすると、試験に受かるにはこれも必要だ、あれも必要だろうとなってしまいます。
だから、仕様規格と性能規格と、ISO9000やISO14000のマネジメントシステム規格との受け取り方を少し変えなくてはいけないかというのが私の考え方です。
品質マネジメントの原則(ISO/DIS9000)
◎顧客指向
◎リーダシップ
◎人々の参画
◎プロセス・アプローチ
◎マネジメントへのシステム・アプローチ
◎継続的改善
◎意思決定における事実に基づくアプローチ
◎供給者との互恵関係
*「品質」の定義品質
ISO/DIS9000(1999.11 国際規格原案)
顧客およびの利害関係者の要求事項を満たすための、製品、システムまたはプロセスに本来備わっている特性の集まりが持つ能力
古いJISの定義
品物またはサービスが、使用の目的を満たしているかどうかを決定するための評価の対象となる固有の性質・性能の全体
もともとISO9000というのは、売り手と買い手の二者間の契約です。商売には、基本契約がありますが、品質に対する契約を結ぶときに、契約書のひな形を示したのがISO9000です。
契約書を書くときに、その中から自由に選んで書くためのガイドラインでした。でもいちいち契約するときに作成するのは大変だから、この会社は品質に対してしっかりした契約ができるような体制を持っていますと第三者がお墨付きを出せば、もっと簡略化できるということで、審査というシステムを考えたのです。それで、受験勉強みたいに一生懸命やらなくちゃいけないと普及したのです。
一番最初の起りは、契約するときに、その中から自由に選びなさいという、きわめて単純な話です。日本ではISOを大袈裟にやりすぎるのではないかと思います。
福武 日本の場合は、本当の趣旨を理解するというより、我も我もと、資格を取るということに重きを置いて、ISOを取得するのは大変だという言葉になっているような気がしますね。
水野 歴史的に品質というものの考え方が変わってきましたね。以前は、使う人だけを対象にした製品の品質保証でした。それが環境問題、公害問題になってくると、周りの人にも影響する。システム製品などでは、使う段階でのサポートや、バージョンアップなど、長期的な付き合い方に変わってきます。製品が単品ではなく、複合製品、システム製品になるわけです。
そうすると、その製品の品質保証をするという考えは、むしろ単発的な製品ではないので、品質を保証できる組織の仕組ができてるということを保証しなければいけません。そのためのマネジメントシステムだと言えると思います。世の中が変わってるからそれに対応しなければいけない。
売り手と買い手の関係は、いいものを売っていればいいという考え方から、長期的な信頼をベースにする関係に変ったわけです。長期的に信頼できるということをお互いに約束しあうようなものです。
ISOの20項目は、ハイラルキーのシステムになっています。4.1には経営者の責任という意思決定のシステムがあって、下の方に物を作る、システムを作るなどの日常の仕事の流れがあって、中間にマネージメントのシステムがある。物を作る中でも教育はしなくちゃいけない。新しく入ってきた人たちに徹底した教育をしなければいけない。物作りとは別の流れの中でもやることがあります。そこをちゃんと区別してシステムも考えた方がいいでしょうね。
| 審査登録の対象規格 | |
|---|---|
| ISO9001 | 設計・開発・製造・据付け及び付帯サービスに関する品質保証モデル |
| ISO9002 | 製造・据付け及び付帯サービスに関する品質保証モデル |
| ISO9003 | 最終検査・試験に関する品質保証モデル |
| ISO9000シリーズの要求事項 | |
|---|---|
| 4.1 経営者の責任 | 4.11 検査、試験及び試験装置の管理 |
| 4.2 品質システム | 4.12 検査・試験の状態 |
| 4.3 契約内容の確認 | 4.13 不適合品の管理 |
| 4.4 文書及びデータの管理 | 4.14 是正処置及び予防処置 |
| 4.5 文書及びデータの管理 | 4.15 取扱い、保管、包装、保存及び引渡し |
| 4.6 購買 | 4.16 品質記録の管理 |
| 4.7 顧客支給品の管理 | 4.17 内部品質監査 |
| 4.8 製品の識別及びトレーサビリティ | 4.18 教育・訓練 |
| 4.9 工程管理 | 4.19 付帯サービス |
| 4.10 検査・試験 | 4.20 統計的手法 |
福武 ISO9000は、品質を保証するシステムを確立するという考え方でよろしいですね。種類としては9001から9003までの種類がある。
水野 今度2000年11月ごろの改定でひとつになります。もうほとんど規格原案はできてます。その9001の中から自分に関連するところだけ引っ張り出してきて、使いなさいというだけの話で。一番最初がそうだったんですよ。それに戻ったんです。
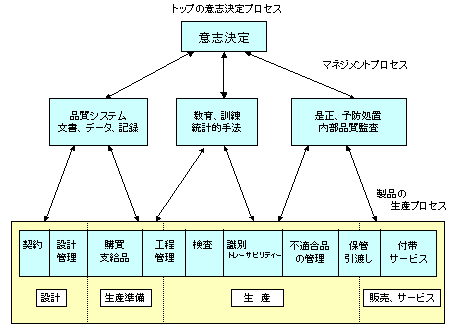
2000年の改定
2000年改定の主な理由は、顧客満足のモニターの必要性、よりユーザフレンドリーな文書の必要性に合致すること、品質マネジメントシステム要求事項と指針との一貫性の保証、組織による一般的な品質マネジメント原則の使用を促すことを強調することが含まれます。
* ISO9001:1994、ISO9002:1994、ISO9003:1994を統合して単一のISO9000:2000とする。
* ISO8402とISO9000-1の内容の一部を統合してISO9000:2000とする。
* ISO9004-1を改定してISO9004:2000
ISO9000は経営改革のツール
福武 取得されたところで聞きますと、取るのも大変だったし、あとあとフォローも大変だということも聞きます。
水野 今までISOのような、契約をしてものごとを決めていくという文化がなかったということもあります。それから、お客様を大事にするということがやや不足しているということもあります。社内の組織が柔軟であるというのは今までなかった。今までこのようなことがなかった企業にはずいぶん役に立ちます。
ただ、ISOがいいというよりも、経営としてどういう革新をしたいか、今どういう経営上の問題があって、その問題をどう直すのか、そこで手段としてISOが役に立つのかどうか、そういう考え方をしなくちゃいけないですね。始めにISOありきで考えないことです。
だからISOを道具として使う、先にやりたい方向を決めてそれを定着させるための道具としてISOを利用する。そういうことだと思います。やはりできないことをいってはいけないですね。ほんとに会社としてやりたいこと、そしてみんなが実現できる内容をやるようにして定着させていくということです。
福武 ISO取得を社内改革の道具にしてやっていけばいいよということであれば、BPRとある意味では似たところもありますね。
水野 BPRよりもISOの方がもっと基盤だと思います。BPRはある程度戦略的ですが、ISOはもっと基盤で基本です。
取得する前に、どんな効果を上げたいかということを考えてる企業は、1/10あるかないかです。何社かやっていますが、会社をこうしたいからISOをやりたいと言われた経験は極めて少ないですね。逆にISOをやるとどういう成果が出ますかと聞かれます。困っちゃいますね。ISOは道具ですから、このトンカチは使い易いですかと聞かれても、それは使い手の腕で、どういうふうに使いたいのか聞きたくなります。
福武 本に書いてありましたが、免許証を取っただけで、ISO9000を取得したからといって優良ドライバーという保証を与えたわけではないと。だからいいものを作るために、継続的に改善をしながら、企業内を改革していかないと本来の精神にのっとっていないということですね。
水野 ええ、そうです。ちゃんと成果を上げて取れば、それ以降も続きます。だから私も興味があるのは経営革新ですね。
ISO取得にあたり経営者の役割
福武 ある意味では、会社とは儲けるためにあると思います。儲けるということは、従業員のためにもいいことだし、儲けようと投資をすることでいい製品もできるし、お客さんのためにもなる。地域に税金で還元できる。会社というのは第一番に儲けるということに焦点をあててその結果すべてがうまくいくというので間違いはないと思うのです。ISOの場合はいい商品をきっちり作るという規格ですから、会社としては、みんなが本当に儲けて幸せな家庭が築けることが永続的にある程度見える形にしたい。それを会社として原点に置きたい。これからそういう会社に変えていくために、やろうということですね。
水野 会社が儲けるというのは、今のように市場が飽和状態になっているときは、売上げが伸びないですね。会社の中を改善していくしかない。生産性をあげるということがありますが、生産性あげるにも限界があります。効率化やBBRなどもそうですが、売上げを伸ばすということではなくて、分母の方の効率をどうやって高めるか、生産性をあげることばかりやっていると、みかけ上の利益率は上がりますが、企業は縮小傾向になっていきます。本当に儲けるというのはどういうことなのかを考えたらいい。戦略を持つというのがものすごく大事です。そうすると、その手段として、外部とのパイプ役のように、表の声を少し聞いて社内に反映できますよとか、外と内とのパイプが顧客指向でつなげましたよ、くらいの利用価値はISOにはあるはずなんです。ISOを利用して、今後どういうふうに儲かる企業にしていくかを考えていくのが面白いことなんですよね。
TQC
福武 TQCとは、どう違うんでしょうか。
水野 TQCというのは、もとはアメリカの品質管理で、戦後日本がアメリカにならってマネージメントの体系にしたのがTQCです。日本の高度成長時代に華々しく花開き、製品も良くなったし成長もしたということで、欧米の人たちが見に来て一生懸命勉強したけど、TQCが基本的にどういうものか分からなかったのです。その辺が少しずつ分かってきてまとめたのがISO9000で、オリジナルは日本だと思っています。ところが欧米はすべて契約文化ですから、TQCは日本人のやり方で、みんなでやろうともっと全社が盛り上がってやりましたね。そういうところがなくなってクールな部分だけ残ったから、だからある程度トーンダウンしてると思いますよ。その割には海外から来た文化を一生懸命日本ではとり入れるくせがあるので、少し加熱気味に一所懸命やりすぎますね。
福武 TQCはどちらかというとボトムアップ的ですね。みんなが集まっていいものを作ろうという運動ですね。だけどもISOの方は性悪説と書いてあったんですけれども、決りを作って決りどおりにきちっとやらなければいいものはできない。ISOで決まったことをTQCなりTQMを使ってもっと良くしていくと、かみ合ってもっといいんだと思うんですが。そういう理解でよろしいですか?
水野 ええ、半分はいいですけが、ISOがトップダウンでTQCがボトムアップというのはそれは誤解です。TQCで一番重視したのはトップ監査、トップの人たちが現状をきちんと把握しなければいけない。それから方針管理というものがありますが、トップから方針を出してそれが末端まで展開されていること。日本が苦手なトップダウンをしようとしたのもTQCですね。だからトップダウンとボトムアップというのは両方あるんですよ。
福武 TQCにも両方があるわけですね。
水野 だから何でもそうなんですけど、TQCができて今度はISO9000っていうのができますよね。そうするとISO9000っていうのがいいんだということを言うために、こっちがだめだということを言わなくちゃいけない。その時の特長としてボトムアップだけをこっちがやっていてトップダウンだってそういう ISOやってる人にもね。TQCを知ってる人と知らない人といますから、随分誤解がありますね。そういうのも困るんですよね。だから必要なところはどんどん取っていけばいいと思うんです。
ISO取得に必要な期間
福武 ISO9000を取得するのに、大体8ヶ月から1年ぐらいでを目標にすると聞いておりますが。
水野 10ヶ月以上かけたことはないですね。途中で中断するような企業はだらだらと長い期間かかります。本気で取ろうという企業は、大体平均で8ヶ月ですね。
福武 8ヶ月で審査を受けて合格するということは、実際やる時間が2~3ヶ月あるとするならば、2ヶ月くらいでマニュアルを作成してすぐ協力をして実施をするということになりますか。
水野 マニュアルを作るのに、1週間に1回ミーティングをして、2ヶ月以上はかけないようにしています。時間をかけるとみんな神経質になりすぎて細かいことまで書きすぎる気がします。一番最初に短時間でマニュアルを作って運用してみて、それで具合の悪い所を直していく、PDCAが大事になってくるんです。
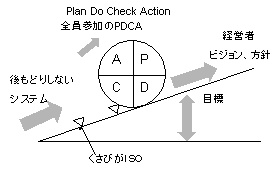
傾斜は目標をあらわしています。企業には必ず目標がありますね。その中で全員参加でPDCAで実践していきましょう。上に引っ張り上げるのが経営者の責任でビジョンや方針です。
後戻りしないように楔を打っていきます。その役割がISOです。やはり後戻りしないでひとつひとつ進んでいくというシステムにしなければいけないということです。
みんなマニュアルに1~2年も時間かけて、いろいろな規定をいっぱい作って、文書管理システムが必要になってしまう。文書管理のシステムがどうして必要なのか、僕には全然わからない。もっと短時間で単純に作ればいいわけでね。
福武 企業には、仕事の仕方を定めた文書があるはずだから、そういうものとうまくリンクをすればいいということですね。新たに作る品質保証に関するマニュアルというのを各項目ごとに1~2ページおきにきちっと掲げておけばいいと、そんなふうに理解したらよろしいでしょうか?
水野 そうです。1ページですむものとすまないものがありますが、確かに今言われたように、マニュアルは1項目に1ページか1ページ半書かれたら十分です。紙のドキュメントである必要はなくて、電子媒体でも構いません。
審査機関
福武 審査機関によって難しい易しいということが相当違うと聞きます。そのために、企業が本来やりたかった改革ができずに、労力だけかかるという形でも困りますしね。また、ある審査機関でも、審査員によってまた全然判断が違うととも聞きます。
水野 人によるばらつきが一番大きいですね。
審査する時には、人を選んでその人に来てもらってあなたはどういう審査をするんですかということを聞いた上で決めるべきです。
福武 そういうこともできるわけですか。
水野 そういうことをするのがISOの精神です。二社間の契約ですから。だから審査機関の方も審査するのに先立って、我々はこういう審査をしたいと思うけどどうだろうと聞くのが常識ですよね。
福武 どこの審査機関と契約しようかという段階でその姿勢を聞くということができるんですか。
水野 もちろん聞いていいんですよ。聞かないで決めるっていうのはおかしな話です。
こんなに審査機関を上にするのは、日本だけだと思いますよ。ヨーロッパじゃ、審査する人が偉いんだといういう位置関係はないでしょう。日本はそんな位置関係が自然にできてしまいますね。
福武 合格させていただこうと思うと、相手を立てなくてはという気がしますね。
水野 そうなんですよね。合格だと思うから、難しい試験を受けるみたいになっちゃうんで、難しくも何ともないんです。義務教育を受ける体力がありますよということを証明すればいい。私はそのうちにホームページで、審査機関から自己PRを取り寄せて、審査機関のベンチマークをやろうかと思ってるんですよ。
ISO取得に必要な費用
福武 取得する際に、認証していただくんですから審査機関に支払う費用がかかりますね。例えば、50人規模ぐらいの企業ならば、どのくらい費用がかかるものでしょうか。
水野 審査の費用というのは、ISOの本部の方で、企業の人員で決まってます。
50人くらいだったら審査費用と登録費用を入れて初年度、120~130万円くらいでしょう。そういうのも何社かの審査機関に見積りを出したらいいですよ。
あと、予備審査というのがあります。本審査よりは安いですね。審査機関は、予備審査を受けるのが普通と言いますが、予備審査を受けるくらいなら本審査を受けた方がいいと思います。
HZSへ

水野 たとえばこちらでおやりになるんだったら、金型屋さんをお客さんにお持ちになっているというから、金型屋さんに対して今までのこちらの対応の仕方でどういう問題があったのか、それを今後どういうふうにしていくのかということを考えてですね、そのプロジェクトを徹底的にやればいいんです。いかに金型屋のお客さんを満足させたかということが証明できれば、それが客観的証拠になります。
そしたらそれでISOはいいじゃないですか。そっちの方から僕は進めるべきだと思うんですよ。それでそっちの方から進めながらさきほど言われた利益を上げるためにはどうしたらいいのかということと結びつけていくと。だから利益の問題って難しいですよね。社内で考えることもあるでしょうし、お客さんをいかに儲けさせるかっていうのも利益でしょうからね。
福武 そうなんです。我々の商品というのはお客様の効率が上がる道具を提供するということですからいくら高くてもそれをやってればもっと効果が出るということだけいえば、買っていただけますね。そういう道具立てを開発して、あるいは他から持ってきて使っていただくというのが商売ですからね。原点が間違わなければ、そういうことをするために私たちはこうしますということを宣言をするということですね。
水野 お客さんのところで、どういう道具立てをどれだけ、何ていうんでしょう、IT装備率というのかそんな感じのどんなものが装備されていればいいのか、こちらでお分かりになってるはずです。で、それが本当に役に立ったかどうか、今後どういうシステムを入れる必要があるのか、お客さんと共存共栄でどういうふうにするのかということを、本当にISOでまともにやったら面白いですよ。
つまりHZSのISOをどうするかを考えると、いろいろ理屈が出てくる。そうでなく、お客様に必要なISOとはどんなものか、その支援のための情報システムをHZSとしてどう提供するかを考える。このようにお客様の立場で考えてみるのがISOと言えるでしょう。
福武 今日、お話をお伺いして、認証取得のプロセスは、まさに、経営者にとってすばらしい経営改革のツールと考えられますね。ぜひまたご指導も含めてよろしくお願いいたします。今日は、どうもありがとうございました。
