略歴

代表取締役社長
最高経営責任者(CEO)
米国オラクル・コーポレーション
上級副社長(SVP)
新宅(しんたく) 正明 様
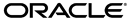
| 1954年9月10日生まれ 大阪府出身 | |
| 1978年 | 早稲田大学政治経済学部卒業 |
|---|---|
| 1978年 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
| 1991年 | 日本オラクル株式会社入社 |
| 1992年 | 取締役マーケティング本部長 |
| 1996年 | 常務取締役マーケティング本部長 |
| 1997年 | 常務取締役製品事業本部長 |
| 1998年 | 常務取締役営業統括本部長 |
| 2000年6月 | 常務取締役事業統括本部長 |
| 2000年8月 | 代表取締役社長 最高執行責任者 |
| 2001年1月 | 代表取締役社長 最高経営責任者 米国オラクル・コーポレーション 上級副社長 |

取締役社長 福武 映憲
福武 E-Businessソリューション分野におけるリーディング・プロバイダであり、革新的E-Businessカンパニーとして、日々変化を遂げられています日本オラクル 新宅社長にITについていろいろなお話をお伺いしたいと思っています。まずは、ITによってこれからの社会はどのように変わっていくでしょうか。
これからのITが社会にもたらすもの(将来のビジョン)
新宅 昔はコンピュータシステム、その次に情報システム、最近になってインフォメーションテクノロジー(IT)という言葉が使われています。
オラクルとしては、ITを漠として捉えるのではなく、インフォメーション(I)とテクノロジー(T)との2つに分けて考えようと思っています。
技術は、素材技術、構築技術、それをベースにした商品技術まであります。これはインテルに代表される半導体技術の急激な高速化高集積化が進んでいますから、20年前と今とでは、パワーに大きな違いがあり、使う道具のスピード感が違うという感じですね。
インフォメーションそのものは、25年前と今と何か変わったかというとあまり変わっていません。
ITのTの革新はずっと行われてきましたが、Iの革新はあまり行われていませんでした。今、このIの革新が起こるトリガーが切られようとしています。これは、情報を蓄える技術やデバイスの価格低下がもたらしますが、やはり情報を流すネットワークの急激な変化だと思います。もし境があるとすればナロウバンドとブロードバンドという言葉に代表されると思います。
環境が変わったときに新しい技術が新しいものを生み出しますが、これからは、新しい情報が、新しい技術や新しいアプリケーションを生み出す時代になります。この情報というのは、何か新たに知恵として生み出せる情報のことを言うこともありますが、私の意味する情報は、管理対象です。企業の情報システムの中で流れているコンテンツは数字と文字ばかりです。それを組み合わせてシミュレーションをしますが、それを超えるものはまだありません。
これからのコンテンツは、音源や映像も含めデジタル化された可変長のデータになり、大きく変わると思います。この変化が企業システムと社会の諸活動に与える影響というのは大きいと思います。
テクノロジーそのものの変化はすごく大きかったですね。誰もが使えるコンピュータになり、携帯電話を生んだのもテクノロジーの変化です。でもこれからは、そこで取り扱っているデータの革新が起こります。今までの延長線上の世界が、次のステップに変わるのが、ITの中のIの革新だと思います。
オラクルが最も得意とするデータベース技術の中で取り扱うデータが、従来言われているマルチメディアではなく、家庭生活や企業システムの中でのマルチメディアがブロードバンドの中で生かされるというような世界になります。設計情報がどのように飛び交うかということもありますね。ファイバー技術や、ブロードバンドの技術の進展によって可能になります。
ITは、道具であり、企業活動や社会の仕組みを変えていく触媒だと思います。
例えば5年間、日本の社会がブロードバンド化や電子政府や電子商取引という国策で非常にフォーカスされたエリアに向かって動いているわけですから、この先を見据えてIT、道具をいかに活用するかは、知恵の勝負になります。技術革新が触媒になって今のような知恵を生み出すということがITの役分であったと思います。結果として、企業の生産性の向上、効率化、スピード化などをもたらしました。
ただ懸念するのは、均一化ということでしょうね。グローバルというのは、今は待ったなしで、競争にさらされない企業はないといっていいくらいの時代です。
ネットワークでグローバルに繋がることで、社会問題に発展することも出てくると思います。例えば、生産業者のように中国に出て行くと人件費が日本の1/25。これで日本の雇用や産業を守れるのか。グローバルを視野に入れた日本企業のサバイバルゲームです。
グローバルを視野に入れた日本のグランドデザインということも、ITの産業から出てきている事柄から、刺激を与えていると思うのです。だからITはITと、国の経営は国の経営、企業経営は企業経営ではなく、企業経営とITが密接にひとつになっています。
今までなかったグローバルに通用する技術やインフラが出てきてしまった。ここが社会にもたらす大きなポイントのような気がします。
ITは、所詮、人間が人間の知恵と英知で取り扱うものであると私は思っております。
製造業へのオラクルの取組み
■中小製造業へのERP導入
新宅 製造業は、日本で一番コンピテンスを持たれ、Eグローバルに活躍している産業だと認識しています。我々の企業向け情報システム、Oracle E-Business Suite(EBS)は、ベースは製造して販売する製販すべての製造業モデルが基盤となって作っています。
ERPを入れるという指示がトップから出たときに、そのゴール設定が不明確なことが多いと思います。何のためにERPを入れるのかというところに立ち返ったときに、経営効率を変えるならコスト、時間、経営の高度化とゴールは決まっているのです。でも、結局、使ってはいるけれども従来型のインプリメテーションに終わってしまっています。
これからのERPインプリメテーションの課題は、いかにカスタマイズの領域を減らすかだと思います。カスタマイズの領分だけ、メンテナンスにお金や工数がかかるというのは常識です。さらに他システムと結合すればするほど、困難な部分は増えます。要するに、接続の部分とカスタマイズの部分が課題です。この課題は今までもずっと尾を引いています。これを解決するには、製品そのものを使い一切カスタマイズしないか、もうひとつは成功のモデルをそのまま使うということです。それがOracle Templateです。
標準のOracle E-Business Suiteでカバーできないところは、Templateのようなものでローコストで導入する。安ければいいというわけではなく、その企業規模と狙いに見合った値ごろ感があると思います。値ごろ感が外れるとだめでしょうし、安いものを入れて無駄な投資をするということもありますから、適切な身の丈のコストを投じて身の丈以上の利益と効率を得るということです。
現実的には、中小規模の製造業にとって投資は大変ですし、時間も割けませんから、短期導入のメソドロジーが非常に重要になります。産業別にメソドロジーは違いますから、その産業の特徴を知らずして、オラクルが簡単に提供できるものではありません。製品の特徴と必要とされる領域が明確になるような製品の提供、アピールが必要です。
WindowsNTプラットフォームは、人事や経理のところで実績が出てきましたから、これからWindowsNTプラットフォームで実装していくということは、オラクルとしても大きな課題です。実績を出して環境を整えていきたいと思ってます。
福武 Windowsなら、技術者がパソコンを含めて同じ感覚ででき、管理がしやすいと言われます。そういったところがポイントだと思います。
新宅 そうですね、注力します。製造業の中でここ3年間くらいで起こったのは会計のところで、グループ経営をするのにいかに等価的にお金の動きを見るか、それをどのように管理するかという、ハブのようなシステムのニーズが高かったのです。
今、製造業は、社内のシステムだけで効率を上げるというのはとても無理ですから、販売系のシステムとサプライヤ系のシステムをドッキングしていく動きがすごく進んでいると思います。
SONYも外の企業がたくさん連結していますから、Weekly経営から、今はOneDayと言ってます。要するに月次では経営できない、週次でも遅いということです。JOBシステムというのはENDtoENDで等価的に見ないとだめだという動きになってきたと思います。
製造業全般でいうと、USトップ1000社の70%がERPを導入していますが、日本のトップ1000社はまだ30%くらいです。早くインフラを整備しないとスピードという点で負けてしまいます。
生産工程のところでいうと、部品表をどう再構築するのか、これは自動車と他の産業は違うと思いますが、企画、デザインの時と詳細設計と製造工程とメンテナンスと部品表がばらばらな形で大変なことになっています。それをどう掘り起こすかというのがひとつのテーマです。これはきわめて大きな、全てのプロセスの効率化にとって非常に重要なことです。
■工場の海外進出
新宅 昔は海外に工場を作ると、オフコンや小型メインフレームベースのその工場用のシステムが入っていましたが、今は、パターンをひとつにしてAという工場のシステム、Aという事業のシステムは一環でつながってますので、ヘッドクォーターのリーダーシップが従来にまして重要になってきていると感じます。ヘッドクォーターで作ったものを海外に展開し、海外の工場をインプリメントしていくという動きが出ています。
我々の製造業を担当しているグループへのお客様からの要求は、グローバルにサポートしてほしいということです。これはサーバをひとつにするという極端なケースは少ないですが、仕組みを一緒にして、変えないでほしいということです。特に製造マニファクチャリングのシステム・インプリメンテーションの基点になるでしょう。
■ナレッジ・データベース
福武 帳票などの数字が自動的にデータベースに入っていくERPは非常にわかりやすいと思うのです。ところがモノ作りでは、経験やカンの暗黙知を形式知としてデータベースに入れてみんなが使うというナレッジ型のデータベースが必要です。あるいは、部品表や3次元データをデータベースを介してみんながコラボレーションする。このような分野で、お客様がデータベースをどう捉えればいいか、アドバイスをいただけますでしょうか。

新宅 ひとつは、共有すべきものは共有することです。共有するときに従来型のCADの3次元データが本当に共有できるかというと、やはりナロウバンド上では結局使い物にならない。
今流行りのコラボレーション・デベロップメントは、自分の仕事そのものも共有資産にしていこうと、24時間その設計過程を進めることができます。3次元データは、ブロードバンド化になると社内だけではなく、社外とも行き来が簡単になります。
設計のどこをアウトソースするのか、何を任せてどれだけのお金がかかるか、セキュリティはどう守っているのかとか、こういう動きになっていると思います。だから共有する資産にする、それが社内である、社外である、そのトランザクションベースに課金が発生する、それから誰が使えて誰が使えないというセキュリティ管理をする、という企業にとっては当たり前の行為が必要です。このようなことをするにはやはりデータベースが必要なのです。人が経験とカンですることではないですね。
今までは目の前にいる人とのコミュニケーションですんだのが、対協力会社とベンダーとの関係も含めたBtoBの中でシステムコンセプトを考えたときに、設計データは、BtoBの電子商取引の大きなコンポーネントになっていくと思います。
もうひとつは、ナレッジをどういうふうに共有するかということです。設計のプロセスを共有するということと、ナレッジの共有は違います。ナレッジは、ナレッジを入れるモチベーションがない限り構築できません。データベースを構築したら仕事が減るのではないか、ノウハウが盗まれるのではないかと、要するに得るものがたくさんあるというよりは、取られるものが多いという発想になっていたと思います。これは企業のトップのディレクションも、サポートするIT産業側のディレクションもまずかったと思います。あなたのためにやってるというのが、なかったと思いますね。
ナレッジデータベースを構築していくには、モチベーションを高めるための、いかに評価していくかという評価のシステムがないとだめだと思います。
企業効率から考えると、ナレッジがデータベース化されて、テクノロジーを取得するスピードを上げていく、社内で蓄積されたナレッジをいかに生産工程に生かしていくかということだと思います。このふたつがデータベース技術を使う根幹になっているような気がします。データベースの中にプロセスを入れ込んでいくということではないはずです。データベースが使える道具になって、どういうふうなプロセスにするかということだと思います。
製造業は、日本のコンピテンスですし、25倍の人件費を取ってそのバリューを提供しつづけるんですから、これは創意工夫が必要です。この人件費ギャップを、情報システムで埋めるのではなくて、情報システムつまり道具を使って、どのようにして創意工夫をもっと高めるかという提案をするかだと思います。
人材育成に対するオラクルの取組み -『物作り』=『人づくり』の観点から-
新宅 まだ16年の会社ですし、我々は数年ごとにどんどん新しい機軸を出して前進変化しています。その変化がオラクルのパワーです。変わらないのは、テクノロジーのリーダーシップであり、それを日本の市場にどのようにアダプトしていけばいいかを考える我々の知恵だと思います。
人というポイントで見ると、日本オラクルでは、当然人が最も大きい資産です。最もお金をつぎ込んでいるのも人です。日本オラクルにとってその時々に活躍できる人材を持ってるというのが一番重要なポイントであり、これは他の会社と同じです。
人材の育成については、新卒を採って育てていくという側面とキャリア組を採用するという側面の2つです。我々のシナリオが変われば変わるほど、欲しい人材も多岐にわたります。ソフトウェアの専業ベンダーにも関わらず、システムインテグレーターの方と同じような幅の人材を持たないと、なかなか会社としてのコンピテンスを広げていけない。人材の育成も随時変えていってるという感じですね。
当社は、一般事業会社に比べれば離職率が高いですね。50年会社にいてほしいとは思いませんが、10年~15年のプランをたてて、経験を積んで独立したいとか、オラクルでスペシャリストとしてやりたいとか、人生のモデルを作ってほしい。そのためにも、人材の市場価値をいかに上げるかということは、ものすごく重要だと思っています。
人材の市場価値を上げていくには、ひとつは、製品技術に熟知することです。製品の市場性があればあるほど、その製品に非常に深い造詣をもった人は高い市場価値があります。
2つめは、営業でもエンジニアでもお客さんとのリレーションシップがとれること。これは非常に大きな財産です。
3つめは、ERPを超えた発想で、世の中の溢れる情報からこれだ!というソリューションをグランドデザインできる人材です。上流コンサルに近いと思います。
人が育つということ、人材価値が上がるということを会社の大きな軸として持つべきだと思います。
オラクルの製品戦略
福武 御社の製品戦略についてお話いただけますか。
新宅 オラクルは、従来から継続するシナリオと新たな時代に向かったシナリオを出し、世に問うということで力をつけてきた会社ですし、失敗もしながら成功を収めてきました。今後もオラクルは、サーバ・テクノロジー製品が機軸になります。データベース技術は企業情報システムの根幹を担っており、オラクルはそのデータベース技術を担ってる会社です。ホビィやパーソナルではなく、エンタープライズというユニットで使える基盤を提供するということです。
我々が最も得意するクラスター技術が本当にクリティカル・サクセス・ファクターになってきたと思います。今想定できる様々な状況の変化、例えば、可変長のストリーミングデータや音声、ASPモデルにあうような次世代型データベースモデルを用意するというのがメイン戦略です。従来の企業内のシステムではなくて、企業間であったり社会のシステムであったりブロードバンドのデジタル・マルチメディア・コンテンツであったり、という大きな流れを支えるデータベースです。
2つめは、E-Business Suite(EBS)です。EBSの中で2つの大きなバリューがあります。ひとつは製品をそのまま使えるように仕上げ、カスタマイズを減らす。2つ目は、我々はテクノロジー・オープンですから、何らクローズでやるつもりはない。ABIをインターフェイスで取り入れながら、最新技術を使ってSIにとっていい設計をしていると評価されたいということです。
もうひとつ側面があるなら、EBS製品を日本市場に売り出して、何が財産になったかというと、データモデルです。金融なら金融のデータモデル、製造業なら製造業のデータモデルがあります。これはTemplateとは違います。こういうデータモデルから設計の材料、情報システム設計の材料を提供していく。何でもできますというのではなく、データモデルを使いながらお客様と理解面との確認をしあう。プロセスで押さえていくモデリングと、データで押さえていくモデリングと両方あると思います。Templateはプロセスで押さえるやり方です。Templateは、付加価値を創造していただけるパートナーさんに扱っていただきたい商品の分野です。我々はデータモデルをきちっと整えていくことが重要で、定着してくればこれをパートナーの方にも使っていただけると思います。
HZSへのメッセージ
福武 3月末にオラクルアプリケーションズR11を使って、EBSをベースに、日立造船の会計、人事、購買のいわゆる事務基幹業務と呼ばれるものを全面的に刷新し、汎用コンピュータも7月20日に撤去しました。
日立造船向けに開発したTemplateをベースに、製造業の受注生産型の企業に対して展開中で、良い方向に動いています。
今後、我々がさらにITコーディネータとして前進していくためのアドバイスなどいただければと思います。
新宅 比較的早くに、日立造船のビッグバン型のインプルメンテーションをされ、しかも、新しい製品を採用していただき、うまくいったということが大変有難かったです。
2つ目は、作る過程から、日立造船の情報システムの本社サイドとHZSサイドがコラボレーションしながらビジネスにするというところがきちっとできていたと思います。我々がSuiteと言っている一部のSuite的なところについては、十二分に経験されたから、その経験を一番売りにしてほしいと思います。
Templateも得意技ですが、これから得意技をいくつか増やしていかれるかと思います。これは日立造船だけではなく、他の会社にもその技術やシナリオを提供できます。我々のパートナーさんにも、そのノウハウをうまく渡していただけるようなウィングを広げていただくと、オラクル系のビジネスが早く立ち上がっていくと思います。新しい機軸を、ぜひ作っていただきたいし、頑張って欲しいと思ってます。
福武 我々としてはERPをひとつのきっかけとして、経験を持っている設計製造のPDMや、生産管理の分野にも、チャレンジしていきたいと思っております。
新宅 今のシステムとプロキャメントとをどうつなぐかが製造業の大きな課題です。経営データの統合管理やその高度利用などがERPに全ての情報が入ってくるわけですから。全ての経営の情報が入ってプロセスの情報が入っている伝票が入ってくる、というところで情報をつないでいかれるのがいいと思いますね。
福武 本日は、お忙しいお時間をどうもありがとうございました。今後、オラクルEBSパートナーNo.1になれるよう頑張りたいと思っています。
