略歴
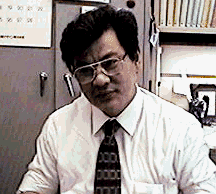
システム情報工学専攻
教授 岸浪 建史様
| 1944年 | 北海道生まれ |
|---|---|
| 1966年 | 北海道大学 工学部 卒業 有限要素法のプログラムを開発 |
| 1971年 | 北海道大学 大学院工学研究科 修了 北海道大学 工学部 講師 |
| 1972年 | 北海道大学 工学部 助教授 曲面の加工の研究に取り組む |
| 1982年 | 工作機械見本市でモデル直接入力方式加工をデモ |
| 1986年 | STEPの標準化活動に取り組む |
| 1987年 | 北海道大学 工学部 教授 |
現在、先生が標準化活動に取り組まれていらっしゃいますSTEPについてお話しをお伺いしました。
商取引における情報
商取引における情報には、物を供給する者と物を使う側である需要者が、その製品に関して完全な情報を持っている場合と、不完全にしか持っていない場合があります。供給者も需要者もその製品に関して完全な情報をお互いに共有している<市場>では、商取引が非常にうまくいきます。
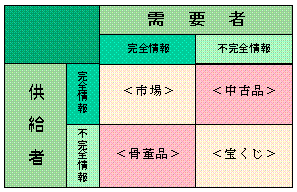
たとえば、<魚市場>はお互いに完全な情報を持っている場合で、捕ってきた魚を即仲買いさんが買える。見ればすぐそれがわかるというビジネスです。
もうひとつは、お互いに不完全な情報しか持っていない場合、<宝くじ>ですね。当たるのか当たらないのか全然わからないものをお互いに取引する。このように、需要者と供給者が情報に対して同じような状況にあるビジネスは、トラブルがなくうまくいくそうです。
ところが、供給者側がその製品に関して完全な情報を持っているが買う側はわからない<中古車>とか、持っている方はどういう価値があるかわからないが、求めている方はよく知っている<骨董品>のようなものは、情報の環境においては非対称といわれています。そういうところでトラブルが起こります。
STEP*1もCALS*2も、「お互いに製品に関して完全な情報を持てるようにしましょう。」ということが目的なのです。
*1 STEP : STandard for the Exchane of Product model data
*2 CALS : Commerce At Light Speed
データ交換の規格
CADのデータ交換にはそれぞれ規格があります。
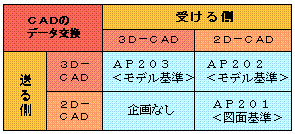
3D-CADの間のデータの交換はAP203という3Dソリッドモデルの交換の規格があります。2次元のCAD図面ですとAP201という規格があります。
このように規格というのは、基本的にお互いが平等になるように主軸上で規定されているのです。
ところが、非対称なところにでもいくつか規格があるのです。3次元のモデルから図面を出す規格がAP202です。また、2次元の図面を入れると立体を作ってくれる製品はありますが、規格はありません。しかし、実をいうと中小企業では図面をもらってきてそれを3次元のモデルにするということをやっているわけですね。
このように主軸上、供給する方も受ける方も対称な環境を作ってあげるというのが今のSTEPあるいはISO*3の基本的な領域です。
*3 ISO : International Organization for Standardization
データ交換とは
データ交換という観点だけでSTEPとかIGESを議論する人がいますが、CADのデータ交換とは、「送る方でいった設計操作が、受ける側でも同じように操作できる」ということであって、ただ単に図面が渡るということではないのです。
そのためにはどうすればいいかというと、現状では一対一にマップするのです。だからIGESは膨大なデータ交換になるし、STEPもそうなっているのです。うまくコミュニケーションするためには、そうならざるを得ません。
そのためのツールはどうするかというと、日本語で書いても英語圏には通じないし、英語で書いても日本では通じない。では、数式やアルゴリズムで全部書けるでしょうか。アルゴリズムと数式という研究は、1980年代にもいろいろなところで行われました。それは、それなりに有効であったと思いますが、やはり限界がありました。
STEPの根幹をなすモデルをどう表現すればいいか、つまりプロダクトモデルという方向に技術が進んでいます。これを支えていくのは記述方式としてはSTEPであり、市場メカニズムを支えるのはたぶんCALSかもしれないしEC*4かもしれない。そのような流れになっていくと思います。
ということは、設計者にとっては、STEPで製品をどのように定義すれば相手側が完全に理解できるか、ということを考えながら設計せざるを得ない時代になるでしょう。技術者にしても需要者にしてもSTEPというテクノロジーが一種の常識的なレベルになってくれることを期待したいと思っているわけです。
*4 EC : Electronic Commerce
マシニングフィーチャー
STEPにはマシニングフィーチャーという概念があります。RP*5とCAMの例で説明しましょう。
点には、曲線上の点、サーフェイス上の点、ボリューム上の点があります。加工は基本的にはこれを使います。
CAMでは、パラメータを変えてサーフェイス上に点を生成する。その点に対してボールエンドミルを用いて加工します。ボールエンドミルは球体ですから相手に対して点接触するわけです。点は点で移すというやり方で物理空間上に点を作る。この点を無限にやっていけば形状ができますね。
これはRPも同じです。RPでは、あらゆるものを点に置き換えて、レーザで個体上に点を生成し、それを積層して形を作るという考え方です。このように、点のみで形状を作成するNC加工およびRPにはマシニングフィーチャーがいらないのです。
しかし、CAMでは、点を生成して物を作るというやり方では能率が悪いのです。線でやれば平面ができるじゃないか、ドリルでやれば一気に穴があくではないか。また、ホールだとか平面だとかボックスだとかいろいろな形をマップする。フェイスカッターだと平面をマップするような工具が用意されています。
形状をそのまま持っているのではなく、加工の観点からある固まりに細分割して、エンドミルにしましょう、ドリルにしましょうということで加工の能率を上げるというのが、現在のSTEPがやっているマシニングフィーチャーの考え方です。
また、途中でこのデータを検証するために人間が読めるような形態に置き換えておこうというのが、APT*6とかNCの考え方です。
加工特徴を考えると、工具を制御する加工と、工具の運動を制御する加工は、意味が違いますので明確に分けなければいけません。
データの与え方、コミュニケーションのあり方についてどういうような技術的な開発課題があるのか、いまSTEPでも誠意研究中です。
*5 RP : Rapid Prototyping
*6 APT : Automatic Programmed Tools
STEPは哲学
1985年の4月に、ワシントンでSTEPの会議があり、東京大学の木村先生が参加され、私も1年ほど遅れて参加しました。その後、いろいろな会議に出ています。STEPは規格というより、何か哲学に近いものだという印象を受けています。記述言語の存在が大きいですね。当時の我々が持っているアルゴリズムとか数式表現とはかけ離れたものでした。知識とか情報とかデータとかが乱れ飛んでいましたが、製品に関する情報をどのように表現すればいいかということを明快に定義し、キチッと整理していますね。
当時のCADシステムではデータの構造、アルゴリズムを速くするための研究が主流でしたが、アルゴリズム研究に限界を感じていました。
このSTEPで、対象をいかに表現するかというモデリングの研究の重要性ということを教えられました。それが大学に対して非常にいい影響でした。
モデリング研究における認知科学、要するに物事をどうやって表現すればいいのかということをSTEPは延々と述べている。哲学に近いところがあります。・その製品をどの観点で見ると何が見えるか
- どういう見方がそれぞれにあるか
- その形をどう表現すればいいか
- 管理するという観点で見ればどうすればいいか
- メンテナンスするとすればどうすればいいか
見方をいろいろ提案し、それに整合性を持たせて統合的にモデル化するための方法論を説いています。
日本の大学では、こういう物の見方を教育してこなかったですね。だから日本もCADシステムのアルゴリズム研究までは良かったのです。でも、それ以降が続かなかったというのは、こういうことにあるのではないかと思っています。
彼らはスタンダードはただひとつだ。正しい物はただひとつだ。と考えています。やはりキリスト教の影響じゃないかと思います。規格はただ一個しかあってはならない。複数個あってはならない。一神教なんですよね。我々は多神教に近いですから、まあいろいろあっていいじゃないの、その場その場でいろいろ使えばと思いますが、それを許さない。妥協しない。
彼らがいうには概念の世界は統合だ。物理的には分散であっても概念は統合する。自分たちの考える世界はただひとつだ。そこに何でも吸収しようというのが強いですね。
キリスト教の宣教師がどんな山の中でも行けるのは、物理的には分散していても考える世界はただひとつだからだ。という非常に強い確信がある。STEPも全く同じような感じがします。STEPは、欧米企業の情報技術による製造業の主導権奪回への手段であるというのは明確ですね。彼らの物の考え方の土俵の中に組み込もうというわけです。広い意味ではCALS全体がそうですね。
ただ、同じ道具を使っている限りは、日本人の方が優秀だと思っています。多少道具が悪くても我々が持っている勤勉さでいくらでもカバーできる。それが強さですから、多少の遅れがあってもかまいません。でも、決定的にツールが劣るとこれは大変です。同じようなツールがある限り、我々は負けないという自負心があります。彼らだってボーイング、GMの一部がやっているだけで、全部がやっているわけではありませんからね。
日本やドイツ生まれのツールがないのは、教育方法に関係するのではないでしょうか。日本もドイツもある型の中に押し込めてしまう画一的な教育ですよね。それで発想の自由度が低くなってしまうのではないでしょうか。
ISOでの会議の場を10年間経験してきた結果から言うと、歴史が同じように繰り返されている。結局植民地戦争なんですよね。物理的な地球の植民地戦争はもう終わりましたが、情報・ネットワークという空間の植民地戦争が今始まっています。その中で占める支配力としてアングロサクソンを中心とした欧米の力は強いという印象を受けますね。
STEPをやっていて不思議に思ったのが、彼らが技術情報をどんどん流してくることです。なぜ、ただでこんなに流してくるのかが最初わからなかったのです。結局は、それになじむ文化を広めることが彼らにとっての利益なのですね。英語を広めたのと同じことです。それを先天的に知っているのです。
STEPはどの分野で必要となっていくか
STEPはどこから入っていくかというと、欧米の植民地化の激しい製造業から入っていくでしょうから、日本でいえば航空機メーカが最初で、その次は多分、自動車部品メーカではないでしょうか。
そしてプラントメーカでしょう。
日本の自動車メーカは大変でしょう。今の作り方、今の環境のもとで最も強い体制を維持しているが故に、新しい体制、新しい環境にどうやって対応するか。もう単なるデータ交換ではないのです。そこのところを知っている人は気がついていますが、なにしろ、自動車は複合体ですから、そこをどうやって変えていくかということが、日本の次の課題でしょう。
自動車が変わると非常に影響力が大きいですね。
確かに自動車メーカは情報化のために多額の投資をしています。だけど現状は、CALS、STEPに投資する割合はその1%にも満たないでしょう。全社の戦略的目標をそこまでかききれていない。製造という段階ではなく、もっと広く顧客一人一人の要求まで製造に反映させようというドラスティックなやり方をすれば、CALSというものが必要不可欠になるのですが。今そこまでは、企業としては意志決定できない。現状をいかによくするかという段階です。
これからは、あちらこちらでSTEP R&Dセンターができてくるんじゃないでしょうか。そのようにならなければ、現状の改革は難しいでしょう。STEP無しでいくということは、鎖国でいきましょうということです。鎖国でいれるわけがありません。
グローバル化

ある日本の自動車メーカでは、日本1チーム、ヨーロッパ1チーム、アメリカ1チームの3シフトで24時間設計活動をしているそうです。日本で8時間設計して、終わったらヨーロッパに渡して設計して、次はアメリカに渡してと、24時間設計をする。ひとつの開発に1/3の時間短縮をする。そのためにはこういう共通技術がないとできないですね。
これは、企業の活動が国の枠を飛び出してしまったということです。
かつては、国という枠組みの中に企業があったのです。国が国民に教育をし、教育を受けた人が企業で奉仕すればよかった。ところが、企業が国を飛び出してしまったものだから、税金をどこに納めればいいのかわからない。国そのものの存在がどういう位置づけなのか。企業があって、国があって、地域があるのかもしれませんね。
日本も英語圏にどんどん進出しています。大学のエンジニアの教育は、日本語だけではだめで英語で教育すべきでしょう。今までは人材を企業の中で育ててきましたが、どうもそうではなく、大学教育のあり方を考え直さなければいけませんね。
日本をベースにした情報プロダクトというのは、日本でしか売れないのです。世界のマーケットからすれば1/50です。それは国際商品ではないのです。
生きていこうとすると、全て英語で書かなければいけない。彼らの生活に合わせたものを書かなければいけない。でも、そのような教育や習慣になっていないですね。逆に、我々は英語で書かれたものを使って消化しています。利用者だからやむを得ないでしょうが。
HZSに期待すること
情報技術(Information Technology)が生産技術を大きく変革するであろう21世紀においては、ユーザが必要とする情報技術を、必要なときに、必要な場所で、瞬時に提供するサービスが重要になるでしょう。
この観点から、HZSには、国産CADベンダーから、設計・生産全般にわたる情報技術のソリューションを提供する企業への脱皮を期待しています。
