福岡造船株式会社様は、造船業としては福岡市の中心に位置するデメリットを、逆に質の充実と付加価値の高い船を造ることで、着実に業績をあげてこられました。特に、ステンレスを使ったケミカルタンカーは、日本で最初に手がけられ、グレードの高いヨーロッパ船の建造など、高い技術力で船を造ることにこだわりつづけられています。
今回は、GRADE導入の背景、GRADE/HULLの運用方法、今後の課題などを中心に、取締役設計部長 早川様、船殻部 部長 河野様、設計部 次長 古賀様、船殻部 現図内業課 岡田様にお話しをお伺いしました。
事業内容について
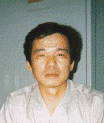
当社は、造船の大手・中手・小手という規模からすると、中手と小手の間ぐらいですね。
材料の納入から加工、製造、組立て、最終塗装まで船一隻すべてを製造して納めます。
船といいましても、貨物船・タンカー・フェリーなどいろいろありますが、当社は特に、ステンレスを使ったケミカルタンカー、リーファー(冷凍貨物船)を主力としています。
ケミカルタンカーは硫酸・リン酸・化成ソーダなどの化学薬品や、石油精製品などを内部のステンレスタンクまたは、コーティングタンクに積載して運搬します。
ケミカルタンカーは昭和42年頃から少しずつ出回ってきました。化学薬品は原油とは違って一挙に何十万リットルも取れるものではないため、中・小型船が運送の中心です。
中手・小手の造船所にとって将来性のある船種ですが、薬品を運ぶわけですから、タンク内部には特殊な加工技術が必要となり、当然、下準備や研究が必要になります。その研究を一早く手がけたことが、ケミカルタンカー建造において一応の評価を受けたと思います。
商船の造船業を開始したときに、輸出船を積極的に取り入れてきました。その結果、海外での評価が日本国内の受注につながっていると思います。
GRADE導入の背景について
当社がNCを検討したのはかなり早くて、14~5年前になります。当時は、現場の体制が整っていなかったので、先送りになり、その後10年は、造船業を取り巻く環境が不安定なため先行きが見えず、NC導入に踏み切れませんでした。
3年前に、1~2年の内に入れようと決まった段階では、ほとんどの造船所が導入していましたから、いろいろな所に行ってNCのソフトとハードを見せてもらい、大変参考になりました。
最終的にGRADEを含めた2社に絞りました。その段階で、将来的なことを考えて2次元システムがいいのか、3次元システムがいいのか、人材の養成の時間、人員の数、自社だけではできないので、バックアップ体制、サポート、いざという緊急のときにはどこがサポートしてくれるのか随分考えました。
最終的には、九州でGRADE/HULLを導入されている造船所が実績をあげられていたこと、その造船所と取引きしている業者さんが当社と共通の業者さんで、すでにGRADE/HULLの操作に慣れていたこと、3次元のシステムでHZSの他のアプリケーションとの組み合わせができる、ということからGRADE/HULLの導入に踏み切りました。
ただ、ワークステーションベースだということで問題はありましたが、将来的にはパソコン版になるということでしたから。
当社と同じ規模の会社の中では、NCの導入がかなり遅かったので、先に導入した会社の方々から、いろいろな問題点を教えていただき、その辺が導入時のトラブルを非常に少なくしてくれました。
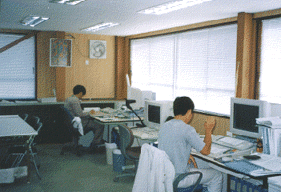
GRADE/HULLの運用方法ついて
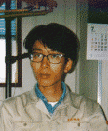
岡田 様
設計からおりてきた構造図を入力して、板厚などの3次元情報をGRADE/HULLで定義して、組立てます。定義するだけでは、NC切断機で切ることはできませんから、NC切断機用のネスティングデータに変換します。
GRADE/HULLを導入する前は、マーキングミス、カッティングミスなどの人為的ミスが避けられなかったのですが、これらが、GRADE/HULLの導入により改善され、バック工事が少なくなりました。
実際に稼働し始めたのは昨年末で、まだ立ち上がりの初年度ですから、NCデータ作成を外注に出さずに作業ができているのは、若いオペレータの努力によるもので、とてもよくやっていると思います。彼らがGRADEを使っていく上でのキーマンとして育ってほしいと思っています。工程が短く、忙しいときは、テンポラリーに応援を頼むような形になることも考えておく必要があります。
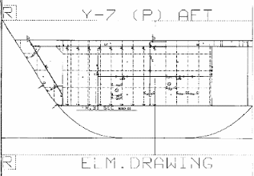
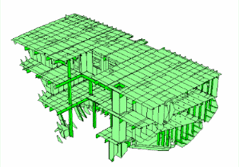
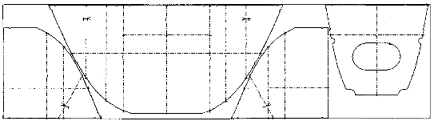
今後の課題について

河野 様
NCは確かにいいです。今まではマーキングしてからいちいち型を写していたのが、そのままばんばん切るのですからね。マーキング、切断などの工程で人が少なくてすみますから、人の融通がつきやすくなりました。
現図までは、このような近代的なシステムになってきましたが、現場を改良していくのが今後の課題です。艤装関係の自動化を早く実現したいと思っています。配管の装置図をCADで書いて、将来的には管の一品図まで取れるようなシステムを目指しています。PlantSpaceをベースとした方が発展性があるということなので、検討してみたいです。
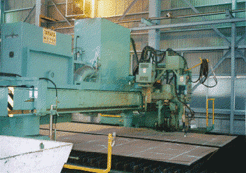
HZSへの要望について
最初見たときのGRADE/HULLの操作性は良かったのですが、現時点では、少し過去のものになりつつあります。最近では、総合システムで配管から艤装まで、設計したものがそのまま全てNCへデータを渡せるようになっています。
図面を書く作業は外注に出しますので、安くて耐久性のあるパソコン版が必要です。ぜひともGRADE/HULLのパソコン化を進めていただきたい。
3次元なので、取り合いで間違えるということは非常に少ないのですが、その分、データを入力して定義をするときには注意が必要です。GRADE/HULL導入後に、設計・現図の初期工数はかなり増加しましたが、後の工程では工数が減少しています。
初期の工数増加は、電算化への過渡期なので仕方がないと考えています。また、一般にNCソフトは、GRADE/HULLだけでなく、他社もすべて大手造船所の中で生まれたものであるため、小型船独特の詳細な部分についての対応が難しいところがありました。
導入後より、HZSの方々とお互いに協力してそのような問題点をひとつずつ解決して現在に至っています。今後とも、協力してよいシステムにしていけば、効率も順調に伸びていくと期待しています。
おわりに
お伺いした本社工場は、福岡市の中心に位置し、門を出ると隣は住宅地です。そのため、夜8時以降は騒音を出してはいけないので作業ができないそうです。このような厳しい環境の中でも、船を造ることにこだわり続けられ、ヨーロッパ船を作るときの苦労など、いろいろなお話をお伺いでき、勉強になりました。
たいへんお忙しいところ、貴重な時間をさいてお話しを聞かせていただき、本当にありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。
会社プロフィール
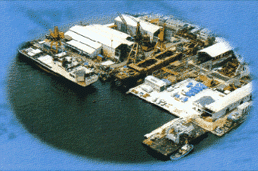
福岡造船株式会社
| 本社 | 福岡県福岡市中央区港 |
|---|---|
| 創業 | 昭和22年11月10日 |
| 資本金 | 9,600万円 |
| 従業員 | 400名 |
| 売上げ高 | 140億(平成8年度) |
| 主な営業品目 | オイルタンカー、ケミカルタンカー、リーファー、旅客フェリー、コンテナ船、セメントタンカー、LPG船、多目的貨物船 |


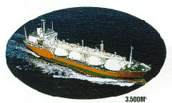
関連するソリューション
関連するソリューションの記事
- 2023年09月29日
-
造船業界向けクラウド型設計・製造ソリューション
「GRADE/HULL Cloud」および「Beagle Cloud」を提供開始
~ 3Dデータを活用した造船業のデジタルトランスフォーメーションを推進 ~
- 2021年07月10日
-
4事業部のご紹介(3)
造船・橋梁ソリューション事業部
- 2020年10月15日
- 造船業界の近未来のソリューションとは
- 2017年04月01日
-
造船業をITで支援する取り組み
~現場支援・艤装設計支援・技術開発~
- 2016年07月01日
- SEA JAPAN 2016 出展報告
- 2015年04月01日
- Beagleを利用した造船業における3D活用状況
- 2004年10月01日
-
3次元船殻CAD/CAMシステム
GRADE/HULLのご紹介
- 1996年10月01日
- 船殻CAD/CAMシステム GRADE/HULL Ver.7.04
